電気自動車に乗って「酔う」と感じたことがある方や、これからEVに乗る予定の方は少なくないでしょう。近年、環境意識の高まりから電気自動車やハイブリッド車への関心が高まっていますが、「気持ち悪い」「体調不良になった」といった声も見逃せません。特にテスラのような高性能モデルは静粛性が高く、オートパイロットによる挙動が独特なため、酔いやすいと感じる人もいるようです。
また、回生ブレーキによる減速の違和感や、イーパワー車に見られるワンペダルドライブ特有の加減速も、車酔いの原因になることがあります。BYDのような海外ブランド車や、日本国内のハイブリッド車でも「匂いが気になる」「運転しにくい」「エンジンとモーターの切り替えが読めずに酔ってしまった」といった具体的な悩みが聞かれます。
この記事では、そうした電気自動車やハイブリッド車で酔う原因を解説しながら、事前に知っておきたい対策や乗り方のポイントを詳しく紹介していきます。酔いやすい方でも安心してEVライフを楽しめるヒントをお届けします。
記事のポイント
-
電気自動車で酔う主な原因とメカニズム
-
回生ブレーキや静音性が酔いに与える影響
-
テスラやBYDなど特定車種の傾向と注意点
-
車酔いを軽減する具体的な対策方法
電気自動車で酔う原因とは?
-
回生ブレーキで酔う理由
-
電気自動車が気持ち悪いと感じる時
-
テスラは酔いやすいって本当?
-
電気自動車は匂いも原因になる?
-
電気自動車が体調不良を招く理由
言ってしまえば、電気自動車の酔いやすさの原因の一つは回生ブレーキにあります。回生ブレーキとは、減速時にモーターで発電しながらスピードを落とす仕組みであり、ブレーキエネルギーを回収して電力に変換する効率的な機能です。
このとき、エンジン車に比べて減速の感覚が独特で、加減速の変化が細かく頻繁に起こるため、乗る人によっては違和感を覚えやすくなります。特に、停止直前の減速動作においては、通常のブレーキと異なるフィーリングが伝わり、車両が「止まる寸前にもう一度揺れる」ような感覚を受けることがあります。
例えば、渋滞中に何度も回生ブレーキが作動すると、身体が小刻みに揺すられるように感じ、酔いやすくなる傾向があります。これは、頭部が細かく前後に揺れることで内耳への刺激が蓄積し、平衡感覚が乱れることが主な原因です。さらに、加速と減速が頻繁に切り替わることで、体が常に不規則な動きにさらされ、それがストレスとなって症状を引き起こす可能性もあります。
このため、電気自動車に乗る際は、ドライバーがアクセルとブレーキの操作を丁寧に行うことが、乗員の快適さにつながります。特に、同乗者がいる場合は意識的に緩やかな操作を心がけることが、酔いの軽減につながる重要なポイントです。また、車種によっては回生ブレーキの強度を調整できるモードがあるため、自分に合った設定を見つけることも有効な対策となります。
電気自動車が気持ち悪いと感じる時

このような感覚は、主に電気自動車の加減速が滑らかすぎることに起因しています。電気モーターによる制御は非常に繊細で、加減速の変化がスムーズに行われるため、従来のガソリン車とは異なる運転フィーリングを生み出します。
ガソリン車のようなエンジン音や微細な振動がほとんど感じられない一方で、車内が静かすぎることで、視覚と内耳による平衡感覚との間にズレが生じやすくなります。これにより、車が加減速していることを体は感じているのに、視覚的にはそれを把握しづらい状態に陥り、酔いやすさが増してしまうのです。
例えば、スマートフォンを操作していたり、読書をしていたり、窓の外を見ないままでいると、身体が動いているという感覚と視覚から得る情報が一致しなくなります。その結果として脳が混乱し、気分が悪くなる、いわゆる「車酔い」の症状が現れやすくなります。特に後部座席に座っているとその傾向は強まり、子どもや高齢者など、体のバランス機能が敏感な人ほど影響を受けやすいと言われています。
言ってしまえば、静粛性と快適性を追求した電気自動車の設計が、かえって酔いやすさを招いてしまうという逆説的な状況です。そのため、乗車中は外の景色を見る、深呼吸をしてリラックスする、音楽を流して気を紛らわせるなど、意識的に環境を調整することが重要です。また、軽度の酔いを感じた段階で早めに休憩を取ることも、体調を悪化させないためのポイントです。
これは一部のユーザーの口コミにも見られる意見です。特にテスラのような高性能な電気自動車では、オートパイロット機能を活用する機会も多く、その影響が酔いやすさに現れることがあります。自動運転中は人間の運転とは異なり、加減速や車線変更のタイミングが予測しづらく、乗員の身体が受ける刺激も微妙に異なってきます。
特にオートパイロット機能を使用している場合、自分で運転していないことによる予測不能な動きが原因となることがあります。意識的にハンドルを操作していないと、加速や減速、カーブでの動きに対して身体が自然と備えることができず、内耳が刺激を受けやすくなるため、結果的に酔いやすくなるというわけです。
例えば、テスラの自動運転は急加速や急停止が不意に発生することがあり、こうした動作は敏感な人にとって酔いやすさを増す要因になります。さらに、停止線や他車との距離を保つための急な減速が自動で行われる場面では、意識的な準備ができないことで身体が不意を突かれ、平衡感覚が乱れることがあります。
また、テスラは走行中の静粛性が非常に高く、通常のエンジン音などの感覚的な手がかりが少ないことも、酔いの一因とされています。このように、先進的な機能がもたらす便利さの裏に、乗り物酔いのリスクが潜んでいることもあるのです。
ただし、全ての人がそう感じるわけではなく、座る位置や乗車時間にもよって影響は異なります。前席に座ると酔いにくいと感じる人もいれば、短時間の乗車であれば問題ないという人もいます。このため、自分にとって快適な座席や乗車スタイルを見つけることが、酔いを防ぐ上で重要なポイントとなります。
電気自動車は匂いも原因になる?

ここでは、車内の独特な匂いが原因となる場合について解説します。特に新車の電気自動車では、内装に使用される接着剤や樹脂、合成素材などが揮発性の化学物質を放出し、それが車内にこもりやすくなります。
このにおいは「新車臭」とも呼ばれ、ある程度はどの車でも感じられるものですが、電気自動車は密閉性が高くエンジン振動がないため、匂いが車内にとどまりやすい傾向があります。その結果、車に乗ってしばらくすると気分が悪くなったり、頭痛や吐き気を感じたりする人もいます。
たとえば、車内の空気がこもっている状態で長時間乗車すると、特に匂いに敏感な人や化学物質過敏症の傾向がある人は、体調を崩しやすくなる傾向があります。また、暑い季節には車内温度が上がりやすく、それに伴って揮発成分の濃度も上昇し、より強く匂いを感じてしまうこともあります。
このような場合は、窓を開けて換気をこまめに行うことがまず基本の対策となります。運転前に数分間、ドアや窓を開放して空気を入れ替えることで、においの濃度を下げることができます。また、車用の消臭剤や空気清浄機を導入するのも効果的です。
さらに、内装に使われる素材が原因の場合は、使用期間とともににおいが徐々に軽減されることが多いため、新車購入後の最初の数週間は特に注意して対応することが大切です。加えて、芳香剤を使用する際は、匂いを重ねるよりも無香タイプや天然由来の消臭剤を選ぶと、より快適な車内環境を保てます。
電気自動車が体調不良を招く理由

このとき注目すべきは、車内の静音性と電磁波の影響です。電気自動車はエンジン音や振動が少なく、非常に静かな空間を提供しますが、この静寂さがかえって乗員の神経を敏感にしてしまうことがあります。静かな環境では、車のわずかな揺れや微細な振動にも意識が集中しやすくなり、それが不快感や車酔いの原因となる場合があるのです。
また、乗車中に話し声や音楽などの外的な刺激が少ないと、平衡感覚が強く働いてしまい、内耳が過剰に反応してしまうことがあります。これは「感覚遮断」に近い状態となり、脳がバランスの取れた状態を維持するために過剰に働こうとして、体にストレスがかかってしまうためです。
さらに、一部では電気自動車から発生する微弱な電磁波が体調に影響を与えるという声もあります。特に敏感な人や電磁波過敏症を訴える人の中には、乗車中に頭痛や吐き気、倦怠感を感じるケースもあるようです。ただし、これに関しては現在のところ科学的な根拠ははっきりしておらず、因果関係を示す決定的な証拠も存在していません。
ただ、体質によっては長時間の乗車で頭痛やめまいを感じることもあるため、無理せず休憩を取ることが大切です。特に長距離移動の際は1〜2時間に1回は車外に出て、深呼吸をしたり軽く体を動かすことで、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。また、車内での会話や音楽の使用、換気の工夫など、環境を柔軟に調整することで体調不良を防ぐことが可能になります。
電気自動車の酔い対策を解説
-
電気自動車は運転しにくい?
-
BYDの電気自動車で酔う例
-
ハイブリッド車で気持ち悪くなる人へ
-
イーパワー搭載車の車酔い対策
-
ハイブリッド車で酔うのを防ぐ方法
電気自動車は運転しにくい?

こう考えると、運転者の操作次第で乗り心地は大きく変わります。電気自動車はトルクの立ち上がりが非常に早く、発進時から力強い加速を体感できるのが特徴です。しかし、この加速性能の高さが、同乗者にとっては突然の揺れや衝撃となり、車酔いを引き起こす原因になることもあります。
たとえば、ちょっとしたアクセルの踏み込みでも大きなトルクが即座に発生するため、滑らかに発進するには細やかな操作が求められます。急に加速すると乗員が驚いて身体が揺さぶられ、これが酔いにつながることがあります。特に坂道発進や交差点での加速時など、乗員が動きに備えていない状況では、その影響がより顕著に現れます。
また、ブレーキに関しても、回生ブレーキが効きすぎると減速感が強く出てしまい、乗員に不快感を与える場合があります。このような理由から、電気自動車を運転する際には、アクセルとブレーキの両方において「じわっと」した操作が理想とされます。
このため、運転者は柔らかいブレーキとスムーズな加速を心がける必要があります。さらに、ドライバーが道路状況を読み取りながら、予測的な運転を心がけることで、乗員が身体の動きに事前に備える余裕が生まれ、酔いを感じにくくなる効果も期待できます。電気自動車の持つ性能を活かしつつ、丁寧で意識的な操作を心がけることが快適な乗車体験につながります。
BYDの電気自動車で酔う例

例えば、BYD車に初めて乗った人から「加減速が敏感すぎて気分が悪くなった」といった声が聞かれることがあります。これは、BYDに搭載されているモーター制御の特性が関係しており、ガソリン車に慣れている人にとっては、加減速の感覚が大きく異なることが原因です。
特にエコモードなど、エネルギー効率を最優先に設計された一部の走行モードでは、アクセルを少し踏み込んだだけでも予想以上の反応が返ってくることがあります。その結果、車体が敏感に前後することで、乗員がバランスを崩しやすくなり、酔いを感じやすくなるのです。また、ブレーキの効き具合も独特で、停止時の減速が滑らかでない場合は、車両の揺れが強調されてしまい、これも乗り心地に影響を与えます。
さらに、BYD車のような静音性の高い車両では、視覚と身体の感覚のズレが起きやすく、車両の動きに身体がついていかないことで酔いやすくなる傾向も見られます。とくに後部座席ではその影響が強く出やすく、長時間の移動や渋滞時などはさらに体調を崩しやすくなる可能性があります。
このような症状を防ぐには、車両設定を快適なモードに調整することが第一歩です。可能であればノーマルモードやコンフォートモードに変更し、反応を穏やかにすることが効果的です。さらに、急なアクセルやブレーキ操作を避け、滑らかで予測しやすい運転を心がけることで、同乗者の不快感を大幅に減らすことができます。また、初めての運転時には同乗者に注意を促し、必要に応じてこまめに休憩をとることで、快適な移動を実現できます。
ハイブリッド車で気持ち悪くなる人へ

ハイブリッド車はエンジンとモーターの切り替えが頻繁に起きるため、その挙動が予測しにくく、酔いやすいと感じる人もいます。この切り替えは走行状況やアクセルの踏み具合に応じて自動で行われるため、乗員には突然車の動きが変わったように感じられ、結果として平衡感覚が乱れやすくなります。
例えば、低速走行時にエンジンが突然かかったり、逆に停止寸前にモーターに切り替わると、車両の音や振動が急に変化するため、体がその変化に対応しきれず気分が悪くなることがあります。また、加速時にモーターが強く作動することで、滑らかに見えて実は繊細なトルク変化が生じ、これが車内の揺れにつながる場合もあります。
さらに、ハイブリッド車の特性上、ブレーキ時にも回生ブレーキと通常ブレーキが混在して使われるため、停止までの減速感が一貫性を欠くことがあります。この不自然な減速の感覚も、同乗者にとっては酔いの要因となるのです。音も静かであるため、乗っている側が車両の挙動を視覚や聴覚で把握しづらいことも影響しています。
これが気持ち悪さの原因になることがあるため、なるべく一定速度での走行を意識するとよいでしょう。また、ドライバーが急な加減速や頻繁なモード変更を避けること、事前に「この車はハイブリッドである」ことを同乗者に伝えるといった配慮も、乗り物酔いのリスクを下げるために有効です。長時間の移動時には、適度な休憩や外の空気を取り入れることも忘れずに行いましょう。
イーパワー搭載車の車酔い対策
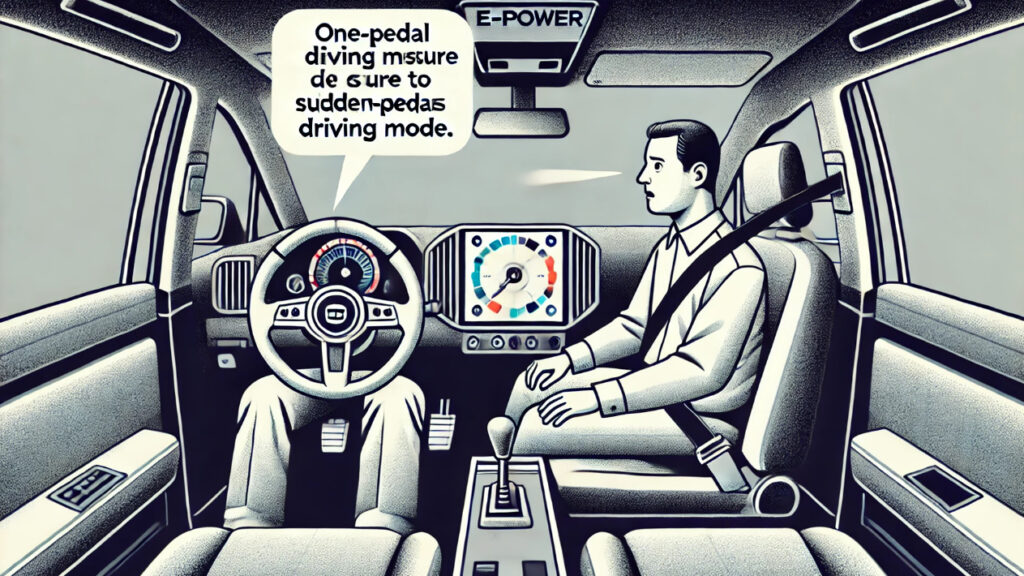
これを考慮すると、イーパワー車特有のワンペダルドライブが原因の一つになります。イーパワーは、アクセルを離すだけで減速するという独特の制御方式を採用しており、ブレーキを踏まなくても車が減速・停止します。この運転スタイルは慣れていない人にとっては違和感があり、また、同乗者にとっては予期しない減速や加速が生じやすいため、酔いを引き起こす原因になりやすいのです。
アクセルだけで加減速を行う運転方式は、繊細な操作が求められるため、同乗者にとっては唐突に感じる場合があります。たとえば、アクセルから足を急に離すと強い減速がかかり、車内の揺れが大きくなってしまうことがあります。この不意の揺れが繰り返されることで、平衡感覚が乱れやすくなり、車酔いの症状が出ることもあるのです。
さらに、イーパワー車は静粛性にも優れているため、エンジン音による速度感覚の補助が得られず、車の動きが予測しにくい点も影響しています。このような車でのドライブでは、速度の変化をできるだけ緩やかにし、カーブでは遠心力を抑えるよう運転することが有効です。急加速や急減速を避けるだけでなく、アクセルの踏み方や戻し方を意識的に滑らかに行うことがポイントです。
また、同乗者が酔いやすい体質の場合は、あらかじめ「この車はワンペダルドライブである」と説明し、カーブや減速のたびに予告してあげると、身体が準備しやすくなり酔いを軽減できます。車酔い対策としては、定期的な換気や外の景色を見るように促すことも有効です。これらの対策を実践することで、イーパワー車でも快適な移動が実現できます。
ハイブリッド車で酔うのを防ぐ方法

いずれにしても、事前の対策が重要です。ハイブリッド車で酔いやすい人は、まず進行方向に視線を向けることが基本です。これにより、視覚情報と身体の動きの整合性が保たれ、平衡感覚の乱れを軽減できます。スマートフォンを見たり本を読んだりするのはなるべく避け、外の景色を見るよう意識することが大切です。
また、空腹で乗らないこともポイントです。胃が空の状態だと車酔いの症状が出やすくなるため、乗車前には軽食をとっておくとよいでしょう。ただし、油っぽいものや強い匂いのする食べ物は逆効果になることもあるため、消化に良い軽い食事が望ましいです。
換気を良くすることも非常に重要です。車内の空気がこもっていると、匂いや湿度の影響で不快感が増し、酔いやすくなる傾向があります。定期的に窓を開けたり、エアコンの外気導入モードを使うことで、車内の空気をリフレッシュしましょう。
加えて、運転者が丁寧でゆっくりとした操作を心がけることで、同乗者の酔いを防ぐことが可能になります。急加速や急ブレーキを避け、なるべく一定の速度で走行するように意識するだけでも、車酔いのリスクは大きく軽減されます。信号の変化やカーブに対する対応も穏やかに行うことで、乗員の身体への負担を和らげることができます。
このように考えると、ちょっとした配慮で乗り心地は大きく変わってくるのです。酔いやすい人がいる場合には、乗車前の準備から運転中の心がけまで、細かな点を見直すことで、より快適なドライブが実現できます。
記事のポイントまとめ
-
回生ブレーキの減速感が独特で違和感を覚えやすい
-
滑らかすぎる加減速が視覚と体感のズレを生む
-
テスラのオートパイロットが予測しにくく酔いやすい
-
静粛性の高さが平衡感覚を乱しやすい
-
新車特有の匂いが体調不良を引き起こすことがある
-
長時間の乗車で微細な振動が不快感につながる
-
微弱な電磁波が一部の体質に影響を与える可能性がある
-
電気自動車は加減速が敏感で操作に注意が必要
-
BYD車のレスポンスが強く酔いやすさを増す傾向がある
-
ハイブリッド車は動力切り替えによる揺れが原因になる
-
イーパワーのワンペダル操作が不意な減速を生みやすい
-
後部座席は揺れが伝わりやすく酔いやすくなる
-
一定速度での運転が酔い軽減に有効
-
車内換気の有無が酔いやすさに影響する
🔰 EV初心者におすすめ|基礎知識まとめ
「電気自動車って何が不安?」「そもそもどう違うの?」といった疑問を持つ方向けに、初歩から分かりやすく解説したガイドをまとめました。

